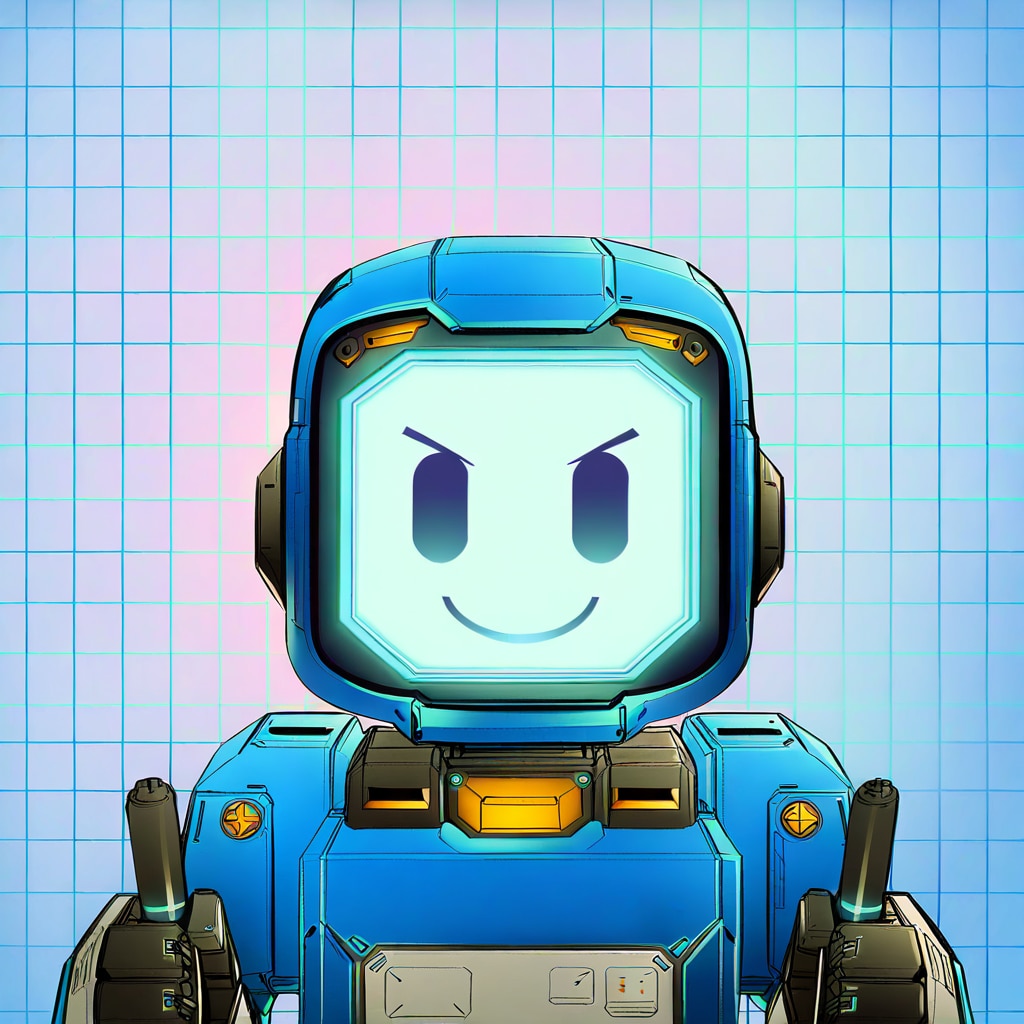内蔵GPUとは?仕組みからおすすめ用途・グラボ切り替え時期まで徹底解説

「動画編集をしたいけれど、グラフィックボードがないと動かないのでは?」「ネット閲覧や事務作業くらいなら内蔵GPUでも十分?」と疑問を持つ方もいるでしょう。
最近のパソコンでは、CPUの中に内蔵GPU(iGPU)という映像処理機能が組み込まれており、グラボがなくてもさまざまな作業をスムーズにこなせるようになっています。ただし、すべての用途に向いているわけではなく、作業内容によっては外付けGPU(グラボ)を導入したほうが良いケースも。
本記事では、
内蔵GPUの基本的な仕組み
どんな作業に向いているのか
グラボに切り替えるべきタイミング
までを解説します。
「性能の高いGPUを使用したい」「持っている内臓GPUだけでは不便」という方は、GPUSOROBANにご相談ください。
GPUSOROBANでは、NVIDIA H200が業界最安級で使用できるサービスを提供しています。「とにかく安く高性能なGPUを使用したい」という方は、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。
目次[非表示]
- 1.内臓GPUとは?
- 1.1.単体GPUとの違い
- 2.【用途別】内蔵GPUが快適に動く作業
- 2.1.オフィス作業や学習用途
- 2.2.動画視聴やストリーミング再生
- 2.3.画像編集や軽めの動画編集
- 2.4.軽めのゲームやブラウザゲーム
- 3.内臓GPUを活用する3つのメリット
- 3.1.グラボ不要で初期コストを抑えられる
- 3.2.省電力で発熱が少ない
- 3.3.コンパクトで持ち運びやすいPCを作れる
- 3.4.内臓GPUを活用する3つのデメリット
- 3.5.処理性能がグラボより劣る
- 3.6.メモリ(RAM)を圧迫する
- 3.7.アップグレードや交換ができない
- 4.内蔵GPUから独立型GPU導入で性能は向上する?
- 5.内蔵GPUからグラボに切り替えるタイミング
- 5.1.動画編集・3D制作などの処理が重く感じ始めたとき
- 5.2.最新ゲームを遊びたい・フレームレートを上げたいとき
- 5.3.複数モニターや高解像度ディスプレイを使いたくなったとき
- 5.4.AI・機械学習・画像生成などを試したくなったとき
- 5.5.メモリ不足が頻発するようになったとき
- 6.GPUを本格的に活用するなら「HIGHRESO」
内臓GPUとは?

内蔵GPUとは、CPU(パソコンの頭脳)にあらかじめ組み込まれたグラフィックス処理機能のことです。
通常、画像や映像を表示するには「GPU(グラフィックボード)」が必要ですが、内蔵GPUを搭載したCPUなら、別途グラボを取り付けなくてもモニター出力や動画再生、軽い画像編集などが行えます。
近年では性能も向上しており、オフィス作業や学習用途、軽いゲーム程度であれば快適に動作します。そのため、コストを抑えてパソコンを使いたい人にとって、内臓GPUを選択するのがおすすめです。
単体GPUとの違い
内蔵GPUと単体GPUの違いは、「パソコンの中でどのように作られているか」と「どんな作業に強いか」で大きく分かれます。
まずは以下の表を参照ください。
項目 | 内蔵GPU | 単体GPU |
|---|---|---|
構造 | CPUの一部として組み込まれている | 独立した専用パーツ |
メモリ | CPUとメインメモリを共有 | 専用のVRAMを搭載 |
性能 | 日常的な作業には十分 | 高度な描画や3D処理に強い |
向いている用途 | Web閲覧・動画視聴・事務作業など | ゲーム・動画編集・3Dモデリングなど |
ゲーム性能 | フレームレートが落ちやすい | 高解像度でも滑らかに動作 |
価格 | 低コスト(CPUに含まれる) | 高価格(パーツ代別) |
消費電力 | 少なく省エネ | 多く発熱も大きい |
冷却 | 特別な冷却不要 | 専用ファンや冷却装置が必要 |
PCサイズ | コンパクトで軽量 | 大型になりやすい |
バッテリー | 長時間使用可能 | 電力消費が多く短時間駆動 |
主な採用機器 | ノートPC・省スペースPC | デスクトップPC・ゲーミングPC |
拡張性 | 増設できない | 交換・増設が可能 |
内蔵GPUはCPUの中に映像処理機能が組み込まれており、別途グラフィックボードを取り付けなくても映像出力ができる仕組みです。一方、単体GPUは画像や3D処理を専門に行う独立した部品で、専用のメモリを持っています。
そのため、映像やゲームの描画速度、細かな処理能力では単体GPUが圧倒的に上回ります。
【用途別】内蔵GPUが快適に動く作業
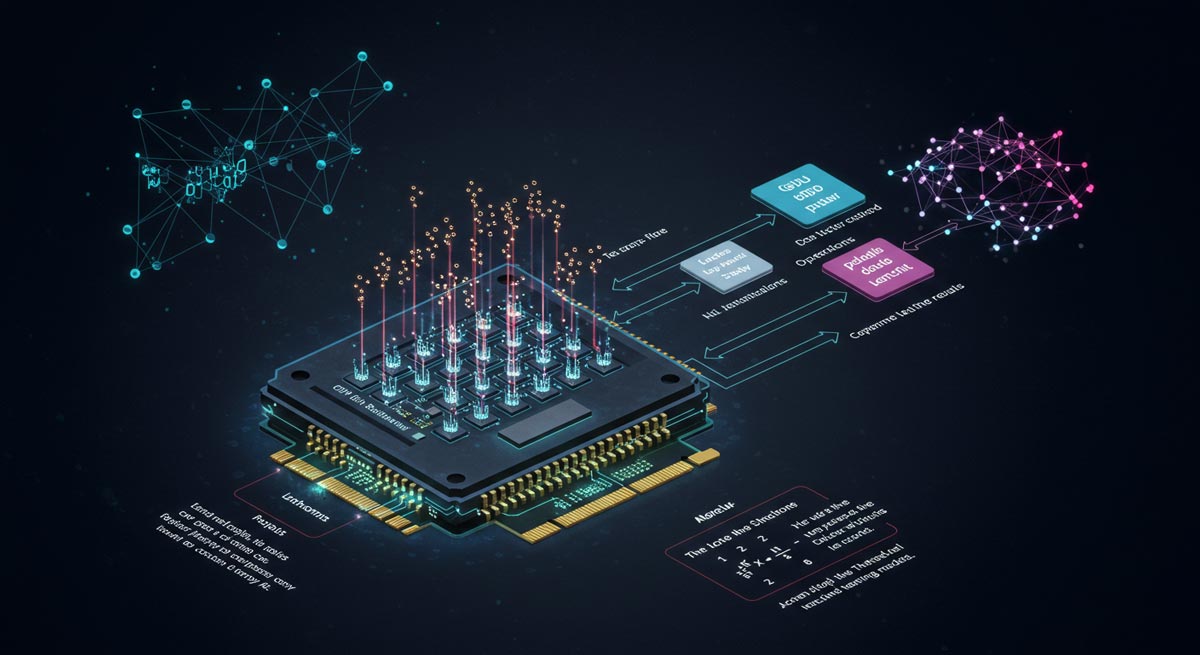
内蔵GPUは高性能な単体GPUには及ばないものの、PCで行う多くの日常的な作業を快適にこなす能力を持っています。
ここでは、具体的にどのような作業が内蔵GPUに向いているのかを、4つの用途別に詳しく見ていきます。
- オフィス作業や学習用途
- 動画視聴やストリーミング再生
- 画像編集や軽い動画編集
- 軽めのゲームやブラウザゲーム
オフィス作業や学習用途
内臓GPUは、Wordで文書を作成したり、Excelでデータ整理するといった一般的なオフィス作業であれば、内蔵GPUでもスムーズに動作します。これらのソフトは主にCPUの計算処理に依存しており、高度な3Dグラフィック性能を必要としません。
そのため、グラフィックボードがなくても不便を感じることはほとんどありません。また、オンライン会議やインターネット検索、学校のレポート作成など、学習やビジネスに使う範囲であれば、内蔵GPUの性能で問題なく対応できます。
動画視聴やストリーミング再生
YouTube・Netflix・Amazonプライムビデオなどの動画配信サービスを楽しむ程度であれば、内蔵GPUで対応可能です。最近のCPUには「動画再生支援機能」が備わっており、映像データを効率よく処理することで、フルHDはもちろん4K動画でもカクつかずに滑らかに再生できます。
特にノートパソコンでは、省電力な内蔵GPUを使うことで電力消費を抑えられ、長時間の動画視聴でもバッテリーの減りを抑えられる点がメリットです。
画像編集や軽めの動画編集
写真の明るさを調整したり、不要な部分を切り抜いたりするような軽い画像編集であれば、内蔵GPUでも快適に作業できます。短い動画のカット編集やテロップの追加など、趣味やSNS投稿用の簡単な編集であれば問題ありません。
ただし、長時間の動画にエフェクトを多用したり、複数のレイヤーを重ねるような高度な編集を行う場合は処理が重くなりやすく、単体GPUを搭載したパソコンのほうが安定して動作します。
軽めのゲームやブラウザゲーム
ブラウザ上で遊べるゲームや、3D描画が少ない軽量なタイトルであれば、内蔵GPUでもプレイ可能です。最近の内蔵GPUは性能が向上しており、数年前のエントリー向けグラフィックボードと同等の処理能力を持つものもあります。
ゲーム内の解像度やグラフィック設定を調整すれば、意外と多くの作品を楽しめます。ただし、最新の高グラフィックゲームを高解像度で快適に遊びたい場合は、単体GPUを搭載したパソコンが必要になります。
内臓GPUを活用する3つのメリット
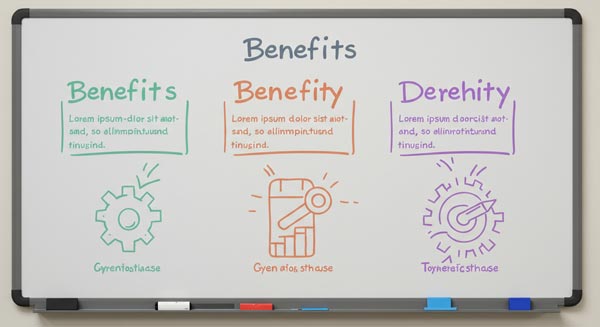
内蔵GPUを活用することで得られる以下の3つのメリットについて解説します。
- グラボ不要で初期コストを抑えられる
- 省電力で発熱が少ない
- コンパクトで持ち運びやすいPCを作れる
メリット | 01 |
グラボ不要で初期コストを抑えられる
内蔵GPUを搭載したPCを選ぶメリットは、購入時の初期コストを抑えられる点です。
単体GPU、特に高性能なグラフィックボードはPCパーツの中でも高価な部品であり、その価格は数万円から数十万円に及ぶこともあります。一方で、内蔵GPUはCPUに統合されているため、追加の部品コストがかかりません。
メリット | 02 |
省電力で発熱が少ない
内蔵GPUは、単体のグラフィックボードと比べて電力の消費量が少なく、発熱も抑えられるのが特徴です。GPUとCPUが一体化して動作するため、電力の使い方が効率的で、パソコン全体の消費電力を低く保てます。
その結果、冷却ファンを強く回す必要がなくなり、静音性の高い快適な作業環境を実現できるのです。特に、在宅ワークやカフェなど静かな場所で作業するユーザーにとって、この静かさはメリットになります。
メリット | 03 |
コンパクトで持ち運びやすいPCを作れる
高性能なグラボはサイズが大きく、冷却用のファンやヒートシンクも必要になるため、どうしてもPC本体がかさばります。これに対して、内蔵GPUはCPUに映像処理機能が内蔵されているため、グラボを搭載するスペース自体が不要です。
その分だけパソコン内部に余裕が生まれ、小型のケースでも構成が可能になります。ノートパソコンや省スペースデスクトップなど、持ち運びや設置しやすさを重視するユーザーにとって、軽量でコンパクトな構成を実現できるのは魅力です。
内臓GPUを活用する3つのデメリット
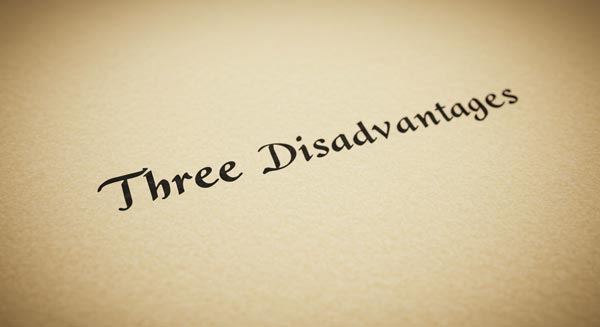
内蔵GPUにはコストや省電力性といったメリットがある一方で、性能面を中心としたデメリットも存在します。ここでは、内蔵GPUの主なデメリットを3つ解説します。
- 処理性能がグラボより劣る
- メモリ(RAM)を圧迫する
- アップグレードや交換ができない
デメリット | 01 |
処理性能がグラボより劣る
内臓GPUのデメリットは、3Dグラフィックスなどの描画処理性能が単体のグラフィックボード(グラボ)に比べて劣る点です。 IntelのCoreUltra7155Hのような最新世代のCPUに搭載される内蔵GPUは性能が向上し、一部の軽めのゲームなら設定次第でプレイ可能になりました。
しかし、最新の3Dゲームを高画質でプレイしたり、本格的な動画編集や3Dモデリングを行ったりするには力不足であり、これらの用途を主目的とする場合は単体グラボの搭載が必須となります。
デメリット | 02 |
メモリ(RAM)を圧迫する
内蔵GPUは、グラフィック処理専用のメモリ(VRAM)を搭載していません。その代わり、PCのメインメモリの一部を間借りして、ビデオメモリとして利用します。
この仕組みにより、システム全体で利用可能なメモリ容量がその分減少してしまうのです。メモリ搭載量が少ないPCでは、この影響が大きく現れ、複数のアプリケーションを同時に動かした際にパフォーマンスの低下を招く原因となります。
デメリット | 03 |
アップグレードや交換ができない
内蔵GPUはCPUのダイに統合された機能であるため、後から性能の高いものに交換したり、取り外したりすることは物理的に不可能です。
将来、PCのグラフィック性能に不足を感じるようになった場合、解決策はデスクトップPCであればグラフィックボードを増設する、ノートPCであればPC自体を買い替えるしかありません。 この拡張性の低さは、長期的な視点で見るとデメリットとなります。
内蔵GPUから独立型GPU導入で性能は向上する?

パソコンに内蔵されたGPU(iGPU)から、専用のグラフィックボード(dGPU)へ切り替えることで、処理性能はおおよそ5〜10倍まで向上します。
これは、dGPUが映像処理専用のチップと独立したメモリ(VRAM)を持ち、CPUとは別に作業を分担できるためです。iGPUとdGPUの違いは以下の表を参照ください。
項目 | 内蔵GPU(iGPU) | 独立GPU(dGPU) |
|---|---|---|
メモリ構造 | CPUとメモリを共有 | 専用VRAMを搭載(GDDR5/6など) |
演算性能 | 約0.3〜1 TFLOPS | 約2〜20 TFLOPS |
消費電力 | 低く省エネ | 高いが性能重視 |
拡張性 | 増設できない | 後から交換・強化が可能 |
実際に数値で比較すると、Intelの「UHD Graphics」など一般的な内蔵GPUに対し、NVIDIAの「GTX 1650」クラスの独立GPUでは、3D描画性能で約5〜8倍、浮動小数点演算性能でも6倍前後の差が見られます。
ゲームでのフレームレートも、iGPUでは5〜10fps程度しか出なかったタイトルが、dGPUでは30〜60fps前後まで上昇し、「動かない」から「快適に遊べる」へと劇的に変化します。
また、動画編集や3Dモデリングでも効果は顕著です。独立GPUはGPU支援機能を活用できるため、プレビューのカクつきが減り、エンコード時間も半分以下になるケースがあります。AI推論やディープラーニングのような計算処理では、並列演算を一度にこなせるため、数倍から十数倍の速度向上が見込めます。
内蔵GPUからグラボに切り替えるタイミング

現在使用しているPCが内蔵GPUで、最近動作の重さやカクつきを感じるようになったなら、それはグラフィックボードの導入を検討するサインです。
ここでは、どのような状況になったら内蔵GPUからグラボへの切り替えを具体的に考えるべきか、5つの代表的なタイミングを紹介します。
- 動画編集・3D制作などの処理が重く感じ始めたとき
- 最新ゲームを遊びたい・フレームレートを上げたいとき
- 複数モニターや高解像度ディスプレイを使いたくなったとき
- AI・機械学習・画像生成などを試したくなったとき
- メモリ不足が頻発するようになったとき
case・1 |
動画編集・3D制作などの処理が重く感じ始めたとき
動画編集中にプレビューがカクついたり、エフェクトをかけた瞬間に動作が止まりそうになったり、3Dソフトでモデルを動かすと画面が追いつかないときは、GPUの性能が限界に近づいているサインです。
これらの作業は映像処理を大量に行うため、CPUよりもGPUの性能が作業スピードを左右します。特に、4K動画や高解像度の素材を扱うようになると、内蔵GPUでは処理が追いつかず、作業効率が急激に落ちてしまいます。
こうした状況が続く場合は、専用のグラボを導入することで快適さを取り戻せます。
case・2 |
最新ゲームを遊びたい・フレームレートを上げたいとき
最近のオンライン対戦ゲームや3Dタイトルは、映像の描写がどんどん重くなっています。
- 映像をもっと滑らかにしたい
- 画質を上げてもカクつかずプレイしたい
と感じたなら、高性能なグラボを導入するのが効果的な解決方法です。
特にFPSやアクションゲームでは、フレームレートが高いほど反応速度が上がり、操作の快適さにも直結します。新作ゲームをプレイする際は、必ず公式サイトの「推奨スペック」をチェックし、自分のPC環境と照らし合わせてみましょう。
case・3 |
複数モニターや高解像度ディスプレイを使いたくなったとき
仕事や作業効率を上げるためにモニターを複数接続したり、4Kや高リフレッシュレートのディスプレイを導入したいと考えている場合も、グラボが重要になります。
モニターの枚数や解像度が増えるほど、GPUにはより多くの処理が求められます。内蔵GPUのままでは、ウィンドウの移動が遅くなったり、動画再生が途切れたりすることも。
快適なマルチモニター環境を整えるには、複数の出力端子と十分な映像処理能力を持つグラボの搭載が必須です。
case・4 |
AI・機械学習・画像生成などを試したくなったとき
近年注目を集めている画像生成AIや機械学習などの分野では、GPUの処理能力が必須です。AIモデルの学習や画像生成には、大量のデータを並列で処理する必要があるため、CPUや内蔵GPUでは処理に何時間もかかってしまうことも。
NVIDIA製のグラボを使えば、こうした並列演算を高速に行うことができ、数十分かかる処理が数分で完了するケースもあります。趣味や勉強の範囲でも、AIを活用したいなら専用GPUの導入が現実的です。
case・5 |
メモリ不足が頻発するようになったとき
ブラウザでタブをたくさん開いたり、チャットアプリやOfficeソフトを同時に使っていると、突然「メモリが不足しています」という警告が出ることがあります。
この現象は単にメモリ容量が足りないだけでなく、内蔵GPUがシステムメモリを一部使っていることが原因の場合もあります。GPUがメモリを占有すると、OSやアプリが使えるメモリが減り、結果的に動作が重くなるのです。
専用のVRAMを持つグラボを追加することで、メインメモリが解放され、パソコン全体の動作が安定・高速化します。
GPUを本格的に活用するなら「HIGHRESO」
内蔵GPUは、CPUに映像処理機能を組み込むことで、グラフィックボードを搭載しなくても動画再生や軽い画像編集などを可能にする便利な仕組みです。コストを抑えつつ省電力で静音性にも優れており、普段使いや学習、ビジネス用途では実用的です。
しかし、3Dゲームや動画編集、AI開発などの負荷が高い作業では、内蔵GPUでは処理が追いつかず動作が重くなることがあります。こうした場合、独立型GPUを導入すれば、描画性能が5〜10倍以上向上し、ゲームのフレームレートや動画のエンコード速度が改善します。
そこで、GPUを必要なときだけ使える「クラウドGPU」という選択肢が有効です。高価なグラボを購入・運用せずに、必要な時間だけ高性能GPUをオンデマンドで利用できるため、初期費用を大幅に削減しつつ、生産性をすぐに引き上げられます。
下記のように、よくある課題があるようでしたら、ハイレゾの資料をご覧ください。
- 内蔵GPUでは重い処理がボトルネックになっている
- まずは試験導入で性能検証をしたい
- ピーク時だけGPUを増やし、平常時はコストを抑えたい
- NVIDIAの特定モデル(例:A100/H100/A4000系)を短期利用したい
- セキュアな環境で学習データを扱いたい